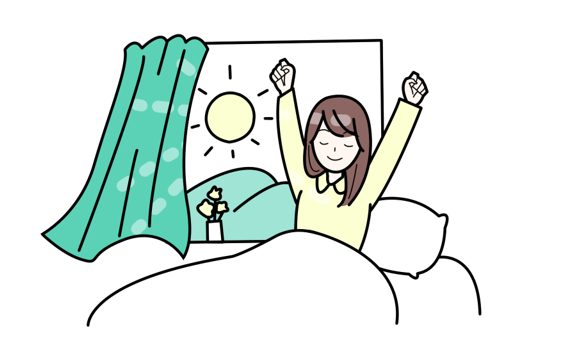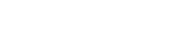年末年始休業のお知らせ
平素より大変お世話になっております。
誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
■休業期間
2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、1月5日(月)以降 順次対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
電話番号変更のお知らせ(大英建設株式会社)
平素より大英建設株式会社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社の代表電話番号が下記のとおり変更となりましたのでお知らせ申し上げます。
■旧電話番号:03-5926-3996
■新電話番号:03-5950-7312
お手数をおかけいたしますが、お控えやご登録情報の変更をお願いいたします。
今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
電気代・ガス代が高騰!実は断熱性能で光熱費でお得に!

真永不動産株式会社です!
ここ数年、電気代やガス代がどんどん上がっています。
「家賃を抑えたつもりなのに、光熱費が高すぎて結局損してる…」なんて声も増えています。
実は、最近注目されているのが “断熱性能”の高い賃貸物件。
見た目の家賃は少し高めでも、結果的に毎月の支出が安くなるケースがあるんです。
1.断熱性能が低い家の落とし穴
・冬は暖房をつけてもすぐに部屋が冷える
・夏は冷房をつけても熱気がこもる
・結果、エアコンや暖房器具をフル稼働 → 光熱費が高騰
たとえば築40年のアパートと、最新の断熱仕様マンションでは、月1万円以上も光熱費が変わるケースも。
2.断熱性能が高い家のメリット
・冬は暖かく、夏は涼しい → 快適な暮らし
・光熱費が抑えられる → 年間で数万円の節約
・結露やカビも発生しにくい → 健康面でも安心
3.どうやって「断熱性能の高い賃貸」を見分ける?
・築年数をチェック
2010年以降の建物は断熱基準が強化されており、省エネ性が高いことが多いです。
・窓の種類を見る
「二重サッシ」「複層ガラス」なら断熱性UP
・物件情報に“ZEH”や“省エネ”の表記があるか
最近は「ZEH賃貸」や「省エネ住宅」といった表記で探せます。
4.まとめ
・電気代・ガス代が高騰している今こそ「断熱性能」が重要
・家賃だけでなく「光熱費+家賃」で比べると賢い選択ができる
・少し高めの家賃でも、快適さと節約の両立が可能
「安い家賃」より「お得な住まい」を選ぶ視点を持つと、これからの時代は強いかもしれません。
空き家×DIY入居ー自分らしい暮らしを叶える新しい住まいー

出典:DIY MAGAZINE 【DIY】築40年のUR団地を40万円でセルフリノベーション!作業内容と費用を公開!/2020.06.06/https://diy-magazine.jp/archives/8954
真永不動産株式会社です!
少子高齢化や都市集中の影響で、全国に増え続けている空き家。
総務省の調査によれば、全国の空き家数はおよそ849万戸(2023年)にものぼり、社会問題として取り上げられています。
一方で、その空き家を「自分で手を入れて暮らす」新しい住まい方が注目されています。それが DIY型賃貸借です。
DIY型賃貸借とは?
DIY型賃貸借とは、入居者が内装に手を加えることを、オーナーが許可している賃貸物件のことです。
オーナーにとっては改修コストを抑えつつ入居者を見つけやすくなり、
入居者にとっては低コストで自分好みの空間を作れるメリットがあります。
DIY型賃貸借のメリット
1.入居者のメリット
・初期費用を抑えられる(リノベ済み物件より安く借りられることも)
・自分好みの空間を作れる(カフェ風・北欧風・和モダンなど)
・暮らしながら技術が身につく(DIYの経験が資産になる)
2.オーナーのメリット
・空き家活用が進む(放置による劣化を防ぐ)
・改修コストの削減(入居者が自分で改装するため)
・物件の魅力アップ(「DIY可物件」として差別化できる)
どこで空き家DIY物件を探せるのか?
実際にDIY可能な空き家を探すには、いくつかの方法があります。
1.自治体の「空き家バンク」
→ 各市町村が空き家情報を公開しており、DIY可の物件も多数。地方移住を考える人におすすめ。
2.民間の不動産サイト(DIY可賃貸・リノベーション可賃貸)
→ 例えば「東京R不動産」「Goodroom」「DIYP」など、リノベやDIY前提の物件を扱う専門サイトがあります。
3.地域のNPO・まちづくり団体
→ 「古民家再生」「地域活性化」を目的にDIY可能な住居を紹介しているケースも多い。
地方でも、移住促進の一環として「DIYリノベーション補助金」を出す自治体も増えています。
注意点と課題
ただしDIY型賃貸借には課題もあります。
・退去時の原状回復をどうするか
・構造に関わる部分の改修は禁止する必要がある
・工事中の安全管理・近隣への配慮
オーナーと入居者が事前にルールを定めて契約することが大切です。
まとめ
空き家問題と暮らし方の多様化をつなぐ「DIY型賃貸借」。
「自分の手で住まいを育てる」という発想は、モノにあふれた時代だからこそ魅力的に映ります。
今後は、オーナーと入居者がうまくルールを作り、双方にメリットがある仕組みを広げていくことが、空き家活用のカギとなります。
賃貸で出来る!簡単な防音・断熱アイデア

真永不動産株式会社です!
「隣の生活音が気になる」 「冬は寒くて夏は暑い」…
そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
ただ、賃貸物件では壁や窓を大きく工事することはできないため、「我慢するしかない」と考えがちです。
実は、ちょっとした工夫でできる防音・断熱対策があります。今回は借主でもすぐに取り入れられるアイデアをまとめました。
1. 窓の防音・断熱

出典:モノタロウ公式
賃貸の中で音や冷気が一番入りやすいのは「窓」。ここを工夫するだけで効果が大きく変わります。
1.厚手の遮光カーテンや防音カーテンを使う
→ 外の音を和らげ、冷気や日差しをカット。
2.窓用断熱シートを貼る
→ ホームセンターや100均でも購入可能。冬の結露対策にも◎
2. 床の防音・断熱

出典:モノタロウ公式
階下への音漏れや床からの冷気も気になるポイント。
1.厚手のラグやカーペットを敷く
→ 足音や物を落としたときの音を軽減。
2.ジョイントマット(防音タイプ)を使う
→ 子どもやペットがいる家庭におすすめ。
3.断熱シートをラグの下に敷く
→ 冬の床冷え対策に効果的。
3. 壁の防音対策

出典:楽天市場
壁の薄さが気になるときは、こんな工夫を。
1.吸音パネルや防音シートを貼る(賃貸用のはがせるタイプ)
→ テレビや楽器の音漏れ軽減に。
2.大きな家具を壁際に置く
→ 本棚やクローゼットを壁に沿わせることで、防音効果を期待できる。
4. 玄関・すきま風対策

出典:モノタロウ
玄関や窓のすきまからも音や冷気は入ってきます。
1.すきまテープを貼る
→ ドアや窓の隙間をふさぎ、防音と断熱を同時に実現。
2.玄関にカーテンを設置する
→ 冷気が室内に入りにくくなり、暖房効率もUP。
まとめ
賃貸だからといって、防音・断熱を諦める必要はありません。
1.窓にはカーテンや断熱シート
2.床にはラグやジョイントマット
3.壁には家具や防音シート
4.玄関にはすきまテープやカーテン
こうした手軽な工夫で、生活の快適さはぐっと上がります。
「音が気になる」「冬の光熱費を抑えたい」と感じている方は、ぜひ今日から試してみてください。
ー賃貸借契約の更新時の注意点ー

真永不動産株式会社です!
賃貸物件に住んでいると、契約期間が終了する前に「更新」の話がやってきます。
しかし、初めて更新手続きをする人や、久しぶりの更新の場合、
「更新って何を確認すればいいの?」
「更新料や家賃の増減はどうなるの?」
「契約内容は変わるの?」
など、疑問や不安を抱える方も多いはずです。
契約更新は単に期間を延ばす手続きではなく家賃や契約条件、退去の可能性などを
しっかり確認する大切なタイミングです。
ちょっとした見落としが、後々のトラブルや余計な出費につながることもあります。
今回は、借主目線で押さえておきたい「賃貸契約更新時の注意点」を、
具体的にわかりやすく解説します。
初めての方でも迷わず対応できるよう、ステップごとに整理しました。
1. 更新のタイミングを確認する
契約書には「更新通知の期限」が記載されている場合が多く、通常は契約終了の1〜2か月前までに更新の意思を家主に伝える必要があります。
期限を過ぎると、自動で契約終了になったり、更新料が発生したりすることがあるので注意しましょう。
2. 更新料の確認
更新時に家主から請求されることがある「更新料」。
金額は家賃1か月分が一般的ですが、地域や物件によって異なります。
契約書に更新料の有無や計算方法が明記されているか、必ず確認しましょう。
3. 家賃の変更
契約更新時には家賃が見直されることがあります。
値上げ・値下げがある場合、契約書や通知書で事前に確認できます。
高すぎる増額がある場合は、家主と交渉できるケースもあります。
4. 契約内容の変更点
更新時に契約条件が変わることがあります。
・駐車場の使用料 ・ペット可否 ・連帯保証人の条件
変更点は必ず書面で確認し、納得できない場合は契約更新前に相談しましょう。
5. 退去の可能性の確認
定期借家契約や特約付き契約では、更新できないこともあります。
更新不可の場合は退去日や手続きを確認して準備しましょう。
退去にかかる費用や手間も考慮して、スケジュールを立てることが大切です。
6. 敷金・礼金・原状回復
更新時には、敷金や礼金の返金・再請求についても確認しておきましょう。
修繕費や原状回復の条件も契約更新時に再確認しておくと安心です。
7. 書面での確認を徹底
更新条件や費用は口頭だけで済ませず、必ず書面で確認してください。
署名・押印を残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
賃貸契約の更新は、家主とのコミュニケーションや契約内容の確認がとても重要です。
更新前に余裕をもって連絡する
家賃・更新料・契約条件の変化を必ずチェック
書面で残してトラブルを防ぐ
これらを押さえておくことで、安心して契約を更新することができます。
ー新型コロナ変異株「ニンバス」今できる対策ー

真永不動産株式会社です!
まだまだ暑さが続く中、体調を崩していませんか?
さて、最近気になるのが、新型コロナ感染の再増加。
最近、全国で新型コロナの感染が8週連続で増加しているとの報道があり、その背景には新たな変異株「ニンバス(NB.1.8.1株)」の拡大が見られます 。
◆「ニンバス」ってなに?
オミクロン株から派生した変異株で、5月からWHOの「監視下変異株」に指定されている株のひとつです 。
現在、検出割合は感染の大部分を占め、約40%以上と報告されています 。
◆まるで「カミソリの刃を飲み込んだ」ような喉の激痛
ニンバスに特徴的なのは「のどの痛みの強さ」。
「カミソリの刃を飲み込むような痛み」と表現されることもあります 。
特に若い方では重症化しにくい一方で、無症状や軽い症状のまま感染を拡げる可能性も考えられます。
◆お盆シーズン以降の注意点と今すぐできる対策
1. 換気の徹底
室内の空気を定期的に入れ替え、空間のウイルス濃度を抑えましょう。
2. マスクをこまめに着用
特に食後の会話や密室では、薄手でもマスクを着用することで喉の負担も軽減できます。
3. 手指消毒&手洗い習慣の再確認
帰宅時や外食後、共用スペース利用後はこまめに手洗い・消毒を行いましょう。
4. 早めの検査受診
「喉の痛みがいつもと違う…」と感じたら早めに検査を。感染拡大の防止につながります。
5. 休養・水分・栄養の確保
体が回復する基盤は「睡眠」「水分」「バランスの良い食事」です。疲労感を感じたらしっかりケアを。
6. 高齢者や基礎疾患のある方への配慮
身近に感染リスクの高い方がいる場合は、さらに予防を徹底しましょう。
お盆以降、感染再拡大が見られる今こそ、基本的な対策の見直し・強化が重要です。
のどの痛みなど違和感を感じたら、「ただの風邪」で済まさず、
検査や対処をすることで、新たな感染拡大の抑止につながります。
夏の疲れをリセット!お盆明けのリフレッシュ方法5選
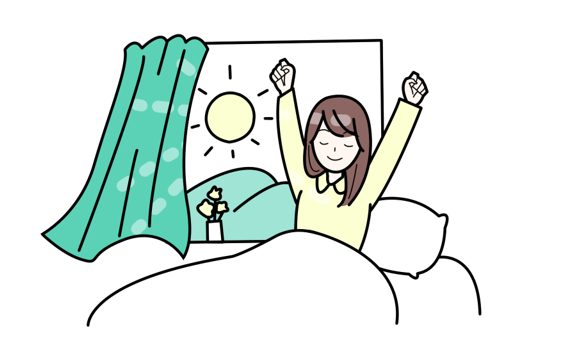
真永不動産株式会社です!
皆様お盆期間中はいかがお過ごしでしたでしょうか?
本日より通常通り営業を再開いたしました。
休業中に頂いたお問い合わせにつきましては、順次対応させて頂きます。
まだまだ暑い残暑が続いていますが、季節の変わり目を快適に迎えるために、
今のうちから「住まいのチェック」をしておくことをおすすめします。
9月も残暑が予想されるため、暑さ対策と秋の準備を両立を心がけていきましょう。
1.エアコンの掃除・メンテナンス
エアコンはまだしばらく活躍する場面が続きそうです。フィルターにほこりが溜まっていると、冷房効率が落ちたり、カビの原因にもなります。
➡自分でできる簡単掃除と、プロのクリーニングをお願いすることも視野に。
2.虫対策の見直し
気温が高い間は虫の活動も活発。排水口の掃除や、侵入口の塞ぎを再チェック。忌避剤の交換や補充も忘れずに行いましょう。
3.防災用品の確認
9月1日は防災の日、非常食・水・懐中電灯・モバイルバッテリーなど、備蓄品の賞味期限・避難経路の確認など、このタイミングで点検しましょう。
4.カビ・湿気対策
夏の湿気でカビが発生しやすくなります。クローゼットや押入れの換気、除湿剤の交換を行いましょう。
5.夏の疲れを癒す住環境作り
まだまだ暑い日が続きますが、観葉植物やアロマディフューザーなどを取り入れて、気持ちを落ち着ける空間づくりもおすすめです。
季節変わり目は、体調も住まいもゆるやかに整えるタイミングです。
小さなメンテンナンスを積み重ねることで、快適な毎日を続けることができます。
お盆明けから新たなスタート、ぜひ住環境から整えてみてはいかがでしょうか?
【知らないと損!】実家を売る前に知っておきたい空き家特例とは?

真永不動産株式会社です!
今回は、月曜日のブログでもお話させて頂いた通り、空き家特例の詳しい内容についてご説明します。
高齢の親が施設に入っていたり、誰も住んでいない空き家が増えている今、実家の売却を考えている人に是非知っておいてほしい制度がこの、「空き家特例」です。
◆空き家特例って何?
「空き家特例」は、一定の条件を満たせば、実家を売って得た利益(譲渡所得)から最大3000万円を控除できる制度です。
例えば、家を売却して500万円利益が出た場合でも、この特例を使えば税金が「ゼロ」になる可能性もあります。
◆どのような場合に使えるの?
以下のようなケースで空き家特例を利用できます。
1.相続によって取得した空き家
・被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた持ち家
・相続開始時点で誰も住んでいなかったこと
2.相続した家を売却すること
・家そのものか、家を取り壊して更地にしてから土地を売る場合
・売却価格が1億円以下であること
3.昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
・旧耐震基準の建物が対象(ただし、耐震リフォームをしていればOK)
4.相続開始から3年以内に売ること
・正確には「相続のあった年の翌年の1月1日から3年を経過する日まで」に売る
◆空き家特例が使えない場合
・被相続人が亡くなるまで他人と住んでいた
・誰かに賃貸していた家
・二世帯住宅で、区分登記されている場合
・相続後に自分や他人が住んでしまった場合
◆使わなかったらどうなる?
空き家特例を使わなかった場合、売却で得た利益に対して最大で20%近い税金がかかってしまいます。
例えば、500万円の利益➡約100万円の税金がかかってしまうというケースも。
制度を知らないだけで、100万円以上の損をしてしまうかもしれません。
◆注意点!忘れてはいけない申告
空き家特例は自動的に適用されません。
売却した年の翌年に、確定申告が必要です。
税理士さんにお願いする場合も、事前に「空き家特例を使いたい」と伝えましょう。
◆まとめ
この家、誰も住まないのに固定資産税だけ払ってる…」
「処分したいけど、税金が怖い…」
そんなお悩みを持つ方こそ、空き家特例を知っておくべきです。
せっかくの制度も、条件に合わず適用できないこともありますし、知らずに期限を過ぎてしまうケースも多いのが現状です。
空き家は、早めに動けば動くほど選択肢が広がります。もし今、「この家どうしよう?」と考えているなら、
「空き家特例が使えるかどうか」をまず一度、専門家に確認してみましょう。
ーお盆の帰省で気づく‘‘実家のこれから‘‘ー

真永不動産株式会社です。
連日厳しい暑さが続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今週末からお盆休みに入る方は、久しぶりに実家に帰省するという方も多いかと思います。
帰省のたびに、少しずつ変わっていく実家の様子にふと気づくこともあるかもしれません。
「家がなんだか古びたな…」
「使っていない部屋が多くて、掃除も行き届いてない」
「親も歳を取ったな…」
そんな何気ない気づきが、実家のこれからを考えるきっかけになることもあります。
今回は、お盆という“家族が集まるタイミング”だからこそ話しておきたい、実家の管理と「空き家問題」について考えていきます。
◆ 空き家の何が問題?
実家をそのままにしておくと、実はこんな問題が…
・固定資産税や維持費が毎年かかる
・建物が劣化して近隣トラブルの原因に
・相続時に兄弟間で揉めることも
・空家特例が使えず損をするケースも
※空家特例についての詳しい内容を今週金曜日のブログでアップする予定です。
◆ お盆は“話すチャンス”
普段は別々に暮らす家族も、お盆だけは一同に会するタイミング。
気まずい話かもしれませんが、将来のために大切な話題です。
◆こんなことを話し合ってみましょう
・親が将来どこに住みたいと思っているか
・実家を誰がどう引き継ぐか
・将来的に売却 or 利活用するか
◆ 選択肢はいろいろあります
「売る」だけではありません。地域によっては、以下の選択肢も
・リフォームして賃貸住宅やシェアハウスに
・短期滞在向けの民泊に活用
・地域と連携したコミュニティスペースに
・解体して土地売却 or 駐車場に転用
◆ まとめ
お盆は、ただ懐かしいだけの帰省ではなく、
“家の将来”と向き合うチャンスでもあります。
「いつか誰かが考える」ではなく、
「今、少しだけ話してみる」ことが、大きな安心につながります。